解説辞書
[] ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ []
- アヴェ王国
- イグニス大陸南部の砂漠にある王国。
- 首都ブレイダブリクは砂漠の中央堆積層上に位置し、ファティマ城を中心に市街が広がる。
- 人口は約40万、民族構成は雑多で異民族や亜人の割合も多い。
- ロニ・ファティマが、いつかまた起こるであろうソラリスとの決戦に備え、興した国家。
- ファティマ王朝によって治められており、代々王家の血筋の者が王位を継承してきた。
- しかし12年前、当時のアヴェ国王、エドバルトIV世と王妃マリエルが、ゲブラーへの協力を拒んだ為に宰相シャーカーンに殺害される。
- その手に政治権限を掌握し、ゲブラーと結託、戦況を五分にまで回復させた。
- ファティマ王家は隣国ニサンの法皇府とは血縁関係にある。
- アクヴィエリア
- 南西のタムズや孤児院があるエリア。多島海とも呼ばれる。
- 過去の頻繁な地殻変動の影響で、陸地が少なく大規模な都市などは存在しない。
- 唯一、世界宗教である「教会」本部や、その関連施設などは他エリアと同様に存在。
- 広い範囲の大陸棚の存在が認められず、陸地が点在する割には水深の深い海域が多い。
- タムズをはじめとする海上都市が多数回遊しているが、これらの都市は規模は違えど、それぞれが独立した自由交易都市として成立しており、その交流は盛ん。
- 「水」を意味する。
- イグニスエリア
- イグニスと呼ばれる、この世界最大の大陸を中心としたエリア。
- 周囲にはニサンやサンドマンズ島などの島嶼が点在し、また大陸棚の分布からは遥かな過去には現在のおよそ1.5倍程度の陸地からなる巨大大陸であったと推測される。
- 大陸はキスレブとアヴェとに分かれ、中央平原及びその両端にそびえる山脈の稜線が国境。
- この2大国は数百年にわたって対立関係に在り、国境線付近は常に緊張状態を保っている。
- 大陸内部はその大半が砂漠からなり、その周囲を肥沃な高原地帯や山脈が取り囲む。
- 主たる都市は大陸内部に、海岸近くには多数の小規模都市や村が両国共に点在している。
- キスレブの領有である北部の大半が冷帯〜温帯気候に属し、南部のアヴェ領有地域の大半は砂漠気候に分類される。
- この地域には、砂漠の堆積層が多数認められ、その中には過去の文明遺産が埋没している。
- ダジルやプリス(小説版)といった都市は、これらの遺跡発掘によって発展したと言える。
- 「火」を意味する。
- 海上都市タムズ
- アクヴィエリアを回遊する巨大船であり、独立した自由交易都市。
- その規模は大きく、ひとつの都市といってもいいほど。
- 住民達は艦長によって統率されており、海底資源や遺跡から発掘した遺物を引き上げるサルベージ活動を生業としている。
- この海域では、引き上げた物資を巡っての血なまぐさい争いも多く、ほとんどの船が武装している。ただタムズは争いごとを好まず、主砲なるものを装備しているものの長い間使っていない。
- ギアも多数保持しているが、これらはあくまで深海作業用で、戦闘には使用していない。
- 同じ海の男としてバルトと意気投合し、両勢力は以後友好関係となる。
- ――艦長自慢のビアホール
- アクヴィエリア広しといえど、これだけ充実した飲食施設は他には見当たらない。
- しかもレストランとしてではなく、ビアホールとして存在しているのも特殊。
- これはひとえに艦長の信条“酒も巧く呑めねえ人生なんざ波に飲まれて消えちまえ!”に象徴されている。
- しかもこのビアホール、ブリッジと直結している。
- キスレブ帝国
- 工業と軍事において他国とは比較にならない発達を遂げてきた国。
- 首都「ノアトゥン」の語源は「造船所」を意味し、その人工は約100万。
- 国家経済の根幹を支えてきた「バトリング」は、現在もデータ収集のため実施されている。
- キスレブ帝都は、中央の総統府を囲むように、一般市街であるA区画、バトリング会場のC区画、D区画などに区画で分割されている。
- この巨大都市の電力供給源は、過去の文明遺産である原子炉。帝都の東にその施設の一部が現在も稼動中。
- ――A区画
- 街中を走り抜ける三輪バギーや人々の服装から想像しうる様に、中〜高所得層市民が集められている。生活水準は高いが、首都部故にD区画とは別の意味で警備が厳しい。
- ――D区画
- 囚人収容を目的に構成されているため、他の区画への出入りは厳しい。
- また、地価が帝都内で最も安価であるため、低所得層の一般民家・亜人、戦災孤児などが集まっている。
- 『教会』
- 教会の前身は、ゲブラーにおいて軍政を担当する一部門として発足した、統合司令部及び各鎮守府付きの幕僚会議。
- ゲブラー発足当時は、間接的支配とは言いつつ軍事活動に主眼が置かれており、各幕僚部はそれに必要な軍政を司る、軍属と文官による単なるサポート組織だった。
- しかし当時のソラリスの国力から、程なく流通コントロールなどの経済支配策を重視せざるを得なくなる。結果として、ソラリス本土の復興に関しても、予想以上に有為なものとなった。
- そして経済支配策へ重きを置くことを決定し、地上がある程度復興した場合に技術、資本的立場から現在の経済優位が逆転することを防ぐため、宗教を利用するプログラムに切り替えた。
- 結果、誕生した帝室特設教務庁は、当初ゲブラーの隠れ蓑としてとりあえず創設されていた「教会」のシステムををそっくり受け継ぎ、より本格的に運用していく事となり、内部的には各幕僚会議を名称はそのままで、各地域の教会司令部として流用する、という形で始まった。
- 現在の統括官は守護天使でもある処刑人(=ミァン)であり、水元鎮守府内に置かれた中央教会内の教皇を通して、各鎮守府が統御されている。
- その活動内容は、教義を利用した民意操作による文化のコントロール、それによる経済のコントロール。
- また、教会はその教義を利用した巧みな民意操作を行っているわけだが、その副次的な効果として、高い能力を持った地上人の教会への帰依、自主的な使役が確認されている。
- 黒月の森
- ステップ地帯と山岳地帯の間に位置する森林で、最も大規模な面積を占める。
- 山岳部に近い部分から針葉樹〜常緑樹で構成された混合林。
- シェバト王国
- イグニス、アクヴィにまたがるエリアの空中を回遊している都市国家。
- 独自の技術により、農耕もその国内で行われている。
- 首都はアウラ・エーペイルと呼ばれ、語源はアウラ=講堂を意味する。
- 先の大戦では反ソラリス勢力の要で、バベルタワーを国土とする地上最大規模の国家。
- しかしディアボロスの侵攻を回避する為、バベルタワー頂上のブロックに一部の国民を収容。これを塔から切り離して戦闘空域から離脱し、「崩壊の日」をしのいだ。
- そして488年前、カレルレンが大戦時にシェバトの機動部隊所属という経歴を利用し、シェバトに来訪。すでに天帝との接触を果たし、ソラリスの上層部にまでのぼりつめていたカレルレンは、ゼファー、元老院等に延命措置を施して逃亡。
- 同年、ゼファーが女王の座に即位し、以降現在に至るまでシェバトを統治している。
- 現在は空中を回遊しながら、頻繁に工作員を地上へ送り込んでいる。工作員は何らかの原因でソラリスに追われている人々をシェバトに導き、戦力として徴用している。
- 元老院は、未だに地上支配の悲願を捨て切れずにいる。
- ――消耗していく軍事力
- 現在はソラリス打倒を唱えつつも、対抗するほどの戦力が残っていないのが現状。
- これは3度に渡って行われたソラリスの侵攻が原因。
- 侵攻の目的は、主にギア・バーラーと、エクスカリバー等の移民船文明の兵器類。
- 三賢者の活躍やゲートの護りによって、侵攻は全て失敗に終わっているが、結果としてシェバトの戦力が大幅に消耗してしまう。
- これはシェバトの国土が空中に孤立した状態だった為、物資の補給が不十分だったのが原因。
- 現在もソラリスはシェバトを狙うが、ゲート攻略が難解である為攻めあぐねている。
- 神聖帝国ソラリス
- 成層圏高度に位置する一大国家。
- その首都は「エテメンアンキ」と呼ばれ「天地の基なる家」の意味を持つ。
- 500年前の大戦で、国土の損壊、人口の著しい減少にさいなまれ、国家体制の抜本的な建て直しが行われた。
- 現在では国家の中枢機能が復活し、地上人をエリア別に支配するプログラムを施行。イグニスを火元鎮守府、アクヴィを水元鎮守府、テランを土元鎮守府がそれぞれ支配・統制している。
- また、減少した人口対策として地上人を労働力として徴収した結果、割合として純粋なソラリス人が激減。その政策として市民層を三層に分割している。
- 俯瞰で見ると、遥か下方に雲を従えた様相だが、反重力システムによって天地が逆になっているため、ソラリスに住み人々には頭上に雲を冠しているように写る。
- ゲートにより通常空間とは隔絶されており、地上からはその存在は確認できない。
- ――広場の様相
- 観艦式など大規模な祭典が行われるアラボト広場。
- 天帝宮から2級市民層へと連なり、周囲を堀が囲む。
- そこにはショッピングセンターなどの施設があり、人々の憩いの場となっている。
- ――地表へと続くシャフト
- 6基のブレード部、天帝宮、3つの市民層などを含む全ての国土を、メインシャフト部分が支えており、このメインシャフトは地上とソラリスを結ぶ重要なパイプの役割も果たしている。
- 細長いシャフト部は地表まで続いており、地上から運ばれた物資・人員などは一度最上部の第3ブロックに集約される仕組みになっている。
- ――国民に対する支配体制
- 増加していく国民を効率よく管理する為に、国民の居住区を3層に分割している。
- 1級市民層を純粋なソラリス人の為の階層、2級市民層を中流階級、一般市民の階層、3級市民層を労働者、別名「働きバチ」が生活する階層とした。
- 2級市民層が造られた目的は、3級市民を対象とした「2級市民への昇格制度」を設けることで、3級市民の労働意欲を煽る為。尚、3級市民が不満の為に暴動を起こすことは殆どない。
- それは地上から徴収された際、完全な洗脳を受けるから。
- こうして膨れ上がった人口を管理、統制し、国家としての更なる繁栄を極める。
- テランエリア
- 北西のデウスがある大陸周辺。最も海域部分の占める面積が広い。
- 遊牧民や狩猟民族といった「地に足の着いた」感のある生活は、基本的に自給自足に近い。
- 気候的な側面から見ても、その大半である海域を寒流が取り巻いているゆえに、最も過酷な地域。
- 「土」を意味する。
- ニサン
- イグニス大陸西方にある宗教国家だが、厳密に言えば国家よりも宗教共同体といえる。
- 首都は存在せず、カテドラルを中心とした信徒の住む住民街が湖の周囲に広がる。
- よって、人口は確定できないが、ニサン正教の関係者に限定すれば1万、近隣に住む信徒までをその数に含めば10万以上となる。
- 法皇府と呼ばれる中央政府によって国策が営まれ、その中心は世襲制の「大教母」。
- もとは一辺境宗教であったニサン教を世界に広がる普遍宗教としたのは、その開祖であるソフィアで「知識の母」とも呼ばれる。
- ――地形的な特徴
- もともとは隕石によって出来た巨大なクレーターで、そこに水が溜まり湖が形成。
- 隕石そのものは岩山として湖の中央部に残り、それが現在の大聖堂の基となった。
- また、湖の周囲に残った僅かな平地と、比較的なだらかな斜面部を利用して町が形成されており、建物は道を挟んで列を成しており、それを囲む切り立った崖は隕石落下時の名残。
- ――中心となる大聖堂
- 隕石であった岩山を削って建立された大聖堂。
- 正確な文献は残っていないが、掘削作業用のギアでもかなりの歳月を要すると推察できる。聖堂内壁は、元が隕石とは思えない程美しい仕上がり。
- バベルタワー
- アクヴィエリア海上に聳える天まで届くといわれる巨大な塔。
- エルドリッジの艦首が突き刺さったもので、各部が90度傾いている。
- ラハン村
- 山麗低層部に位置するするので、民家の造りに特徴がある。
- 牛の飼育や名物カミナリダイコンなどの出荷収入は村の貴重な収入源となっている。
■ TOP ■
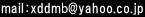
Copyright © 2008 SQUARE ENIX CO., LTD All Rights Reserved