解説辞書
[] ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ []
- アハツェン
- 指示系統を外部の人間の判断に依存していたゼプツェンとは対照的に、自動行動用のメインフレームに人間の脳組織を採用した初めての機体。
- カラミティ同様の飛行形態への可変機構が採用され、機動力が高められている。
- ゼプツェンと同じ装備に加え、新規開発されたグラビティライフルを腕に追加。
- 自律行動するギアとしての完成体とも呼べる機体。
- 名称はドイツ語で「18」という意味。
- アルカンシェル
- <搭乗者>ストーン
- 海域制圧の主力となるべく開発されたギア。
- 通常時は海上を航行し、戦闘時は空中活動へ移行することで長時間の活動が可能。
- 腕部のツメから発する機能障害ジャマーは、敵となる機体の中枢回路に電磁波を送り込み、100%の能力を出させないようにするもの。
- シタンが設計主任となったものだが、刻印砲はストーンの手に渡った後取り付けられた。
- アンフィスバエナ
- <搭乗者>カレルレン/ラムサス
- カレルレンのギアがアニマの器「ユダ」と融合して誕生したギア・バーラー。
- 尻尾の先が硬質化し、刀剣になる。
- 名称は頭と尾の両方に顔をもつ蛇より。ギリシャ語で「両方向に進める」の意味。
- ヴィエルジェ
- <搭乗者>エリィ
- ゲブラー次期主力ギアの主兵装として、トライアル中の新型攻撃デバイス「小型エアッドシステム」の試験運用を目的として設計開発されたギア。
- ヴィエルジェには、基礎データの収集目的で試作された「A1型」、先行量産された「A2型」、実質的量産型となった「B型」などの機体バリエーションが存在する。
- エリィの搭乗する機体はA2型で、士官専用機として少数が実戦配備されたもの。
- また、攻防両用のエアッドを両肩に搭載したC1型と呼ばれる機体も僅かながら生産されており、この機体はミァンによって運用されている。
- A2型に搭載されているエアッドシステムは、試作機であるA1型のものが流用されており、最大12基の攻撃デバイスの同時操作が可能。
- 名称はフランス語で「乙女座」という意味。
- ヴェルトール
- <搭乗者>フェイ
- ORヴェルトールを基に、フェイ(イド)専用機としてグラーフが秘密裏に開発、建造。
- 基本設計はORを模した構造で、エクステリアのかなりの部分が酷似している。
- また、その主機となるスレイブジェネレーターは、ORに搭載されている物の純粋レプリカで、構造素材の違いこそあれ、その出力係数はオリジナルのそれに匹敵する。
- とは言え、機体の構成部品が、他のギア・アーサーと同様の素材で造られており、最大出力時に機体にかかる負荷は絶大で、材質面での脆弱性は否めなかった。
- 機体剛性の問題は、エクステリアの外骨格化と可変機能を設けることで補ったが、稼働時間の延命行為でしかなく、打開案として平時に出力を抑える為のリミッターが設けてある。
- 名称はドイツ語で「事象世界、宇宙」という意味。英語では「world all」となる。
- ヴェルトール・イド
- <搭乗者>イド
- ヴェルトールがそのジェネレーターの最大出力を発揮するための形態。別名イド・モード。
- その本来の能力――ORに匹敵するパワーを発揮するためには、機体剛性が決定的な程脆弱で最大出力での機動戦闘における過負荷は深刻で、戦闘後に行動不能に陥るほど。
- 機体剛性の向上を図り、従来のフレームは一次装甲と一体化、単体張殻<モノコック>構造とし、強度を確保。さらに二次装甲のエクステリアにも、フレームの機能と駆動機構を移植し、外骨格として機能させた。
- 内骨格と外骨格、二重のフレームと駆動機構の併用により機体剛性を得るに至った。
- しかし、もう一つの深刻な問題が、ジェネレーターの発生させる膨大な熱量の冷却問題。
- レプリカとはいえ、ORのそれと同様で下手をすれば機体そのものが融解させかねない代物。通常機器で構築されているヴェルトールにとって、その冷却は非常に困難なもの。
- そこで、通常のラジエーターと併用する形で、新たに電磁波冷却システムを搭載。発生した熱エネルギーを機体装甲表面と背部冷却ユニットから電磁波として空間に放出。
- 具体的には、発生熱量の約3分の2が電磁波として放出され、3分の1が通常ラジエータによって冷却。残りは新たに設計された蓄積器<コンデンサー>内に蓄えられ、機体の稼動に再利用されている。
- また、この冷却システムから放出される電磁波スペクトルには、可視領域の波長も混在しており、機体の赤熱現象や背部から発生する光翼状の発光現象、機体を包む周辺空間の発光現象はこの為。
- ヴェルトール2<セカンド>
- <搭乗者>フェイ
- 損壊したヴェルトールを回収し、トーラとバルタザールによって修復された機体。
- 墜落の衝撃により、一部その機能に変調をきたしたスレイブジェネレーターが、膨大な余剰出力を解放していることに気付いたバル爺がブラックボックスの解析を行った。
- その結果、イドモード時の出力に固定されたまま稼動している事実が判明。
- また、常時固有の振幅数を持った電磁波様の波形が発信されていた。
- これを搭乗者からのマーカー発信と同時に、SJからも発信されるバイパス波の一部であると確信。ジェネレーターの機能を調整し、そのまま制御可能な仕様へと変更した。
- 機体には、時間と共に増大していくバイパス波が極大とならないよう、一定時間が経過すると、ノーマル状態に戻す遮断機能が付加された。
- イドモードは、暫定的な措置であり、本来の力に比較すれば幾分か劣っている。
- 尚、機体剛性の問題は、外骨格として機能していた二次装甲をデフォルトにすることで解決され、その材質もアンドヴァリから得られたデータを基に、ナノマシンによって新素材へと変更されている。
- ヴェンデッタ
- <搭乗者>ラムサス
- ワイバーンがアニマの器「ゼブルン」と融合して誕生したギア・バーラー。
- ラムサスにより、その力を100%引き出された完全体。
- 英語で「怨念、長期にわたる不和」の意味。
- エクスカリバー
- エルドリッジに搭載されていたプレアスター級機動巡洋艦。
- 同型で2隻が搭載されており、シグルドが使用したのは2番艦にあたる。
- シェバトにより発掘、改修されており、対ソラリス戦で活躍した。
- 対して1番艦の方は、500年前の大戦でソフィアが搭乗し、凄絶な最期を遂げている。
- 基本的な艤装は両艦共通だが、唯一の相違点が艦首衝角(ラム)の有無。
- 2番艦には実に2000シャール近い長大なラムを取り付けることが可能となっている。
- 本来このラムはユグドラシルIVがギア形態時に、剣として用いることを前提とした武器。
- すなわちエルドリッジに搭載されていた艦艇は、強襲揚陸艦(ユグドラシルIV)がギアとなり、機動巡洋艦(エクスカリバー)がその武器になるように、トータルコーディネートされていた。
- 名称はアーサー王が持つ伝説の剣より。
- エゼキエル級戦闘艦
- ソラリス製艦艇群の中でも最大を誇る、超弩級の空中戦闘艦。
- その威容は艦艇というよりは「移動要塞」とでも言う方が似合う。
- 劇中ではタムズ艦長らから「タコつぼ」などと不名誉な異名を付けられていた。
- 最高司令官カレルレンが搭乗するソラリス艦隊の旗艦とあって、それに相応しい優れた攻撃力・耐久力・機動力を誇っている。
- 現在の世界情勢でソラリス軍が艦隊戦を行うこともないだろうが、いざその時となれば、この戦闘艦が他国の脅威となるのは間違いない。
- E・アンドヴァリ
- <搭乗者>ロニ/バルト
- 500年前にロニが駆っていたギア・バーラー。融合したアニマの器は「ダン」。
- 崩壊の日には攻撃部隊の主力として、その強大な威力を振るった。
- アヴェ、ニサンに伝わる王国の危機を救うと言われる至宝。
- アニマの器を奪われて一時は動かなくなるが、ゼノギアスから得られたデータを基に強化・再現される。
- 名称は北欧神話に登場する黄金の指輪を持つ小人より。
- E・シューティア
- <搭乗者>リコ
- シューティアがアニマの器「ガド」と融合して誕生したギア・バーラー。
- 頭に羽が付き、背部のロケットが無くなっている。
- アニマの器を奪われて一時は動かなくなるが、ゼノギアスから得られたデータを基に強化・再現される。
- シューティアのロケットは、途中で切り離してからバーラー化する予定だったらしい。
- エルドリッジ
- フィラデルフィア級超大型恒星間航行船二番艦。
- 企業が所有している、宇宙移民計画のために建造され、その全長は100kmに及ぶ。
- 接続起動実験中に暴走したデウスシステムを分割移送するために、軍部に徴収される。
- コロニーのような居住空間部と管制部に分かれた構造になっている。
- 航行中のあらゆるトラブルに備え、人工電脳ラジエルを配備。
- デウスを検査星へと移送途中、デウスの暴走によって舞台となる星へと墜落する。
- ――艦首ブロック「バベル」
- エルドリッジ程の船体になると、各主要ブロック毎に自立航行可能な造りとなっている。
- その1つが艦首ブロックで、劇中のバベルタワーがこれにあたる。
- また、大規模なプラント用HLVが搭載されており、シェバトを構築する中央ブロックとなった。
- ――中央ブロック「マハノン」
- エルドリッジ全体を統括するコンピュータ「ラジエル」が収納されている。
- バベル同様、自立航行機能により軟着陸を果たしている。
- ラジエルには、異星文明の兵器・生体情報を始め、デウスに関する資料も記録されていた。これらの情報がヒトに漏れることを恐れたガゼル達は、ゲートによって行き来をできないようにした。
- E・フェンリル
- <搭乗者>シタン
- シタンがソラリス守護天使時に与えられたギア・バーラー。
- 地上に降りた時にガスパールの元へ預けておいたもの。
- 剣を装備しており、高い攻撃力も持つ。融合したアニマの器は「アシェル」。
- アニマの器を奪われて一時は動かなくなるが、ゼノギアスから得られたデータを基に強化・再現される。
- 名称は北欧神話に登場する巨大な狼で、悪神ロキの息子「フェンリル」より。
- E・レグルス
- <搭乗者>ソフィア/エリィ
- 500年前にソフィアが同調したギア・バーラーだが、乗ることは無く、シェバトに保管されていた。
- シェバトを訪れた際にエリィと同調する。
- 搭乗を拒否したのは、無意識的に「対存在」である自分と「アニマの器」との関係を感じ取っていた為。
- 融合したアニマの器は「ディナ」。
- E・レンマーツォ
- <搭乗者>ビリー
- レンマーツォがアニマの器「ヨセフ」と融合して誕生したギア・バーラー。
- 頭の角が固く鋭利になり、背部のマントは翼へと変わっている。
- アニマの器を奪われて一時は動かなくなるが、ゼノギアスから得られたデータを基に強化・再現される。
- オピオモルプス
- <搭乗者>ガゼル法院/ミァン
- 500年前に法院のギアがアニマの器と融合して誕生したギア・バーラー。
- 下半身が蛇のようになっており、ソラリス潜入中にその姿を見ることが出来る。
- カレルレンにより、ナノマシンによる再生能力が付加されている。
- OR<オリジナル>ヴェルトール
- <搭乗者>ラカン/グラーフ/ワイズマン/カーン
- 約500年前、ラカンのギアがアニマの器「ナフタリ」と融合して誕生したギア・バーラー。
- 一度はゾハルとの接触によりその能力を極大にまで引き出され、ゼノギアス同様の形態変化をした。背部にある蝙蝠状の翼はその時の名残で、現在は飛翔時の制御と防御時の盾として機能している。
- 自己完結した循環系によって、発生熱量の99%以上が再度機体駆動用のエネルギーとなる。
- ――グラーフの「力」
- 「我の拳は神の息吹!“墜ちたる種子”を開花させ、秘めたる力をつむぎ出す!!美しき滅びの母の力を!」
- “墜ちたる種子”とは、ゾハルのエネルギー端子であるスレイブジェネレーター。
- その出力値を引き上げることが出来るグラーフの力を暗に示している。
- “滅びの母”とはデウスそのもの、グラーフがデウスを兵器の象徴と見たということ。
- カップナイト
- <搭乗者>フランツ
- 巨大な左手は、遺跡発掘現場に用いられる削岩用のアームを戦闘用に改造したもの。
- 格闘戦では絶大な効果を発揮するため、部隊内においてはソードナイトと共に敵陣に切り込むことが多い。
- カラミティ
- 搭乗者を必要とせず、自律行動する人工頭脳を搭載したギア。
- 設計者はバルタザール。対ソラリス用に「単独戦闘可能なギア」という目的で設計。
- サバイバビリティーを高める強固な装甲、対多数にも対応できるようにミサイルポッドを装備。
- 増加した装備重量による機動力の低下を補うため、強力な飛行ロケットを装備している。
- キファインゼル級
- アヴェの国境艦隊旗艦。軍司令官ヴァンダーカムの乗艦。
- 完全に砂上航行専用にカスタマイズされ、平地や空中を移動する機関は持たない。
- それに代わって推進外輪が前後に各2つずつ装備され、砂上では優れた機動力を見せる。
- また、とりわけ目を引くのがブリッジ前に鎮座する巨大な主砲。
- 直径8シャールにも及ぶ巨大な砲口からは、駆逐艦にも匹敵する7200カーンもの質量が投擲可能で、対都市などの面制圧任務では絶大な威力を発揮する。
- 装甲目標に対しても短砲身故の初速の遅さを弾体質量が十二分に補い、直撃すればソラリス艦のポリカーボナイト複合鋼さえ紙のように易々と引き裂くことが出来る。
- また、親子式のクラスター榴弾である「三式弾」を使用することで対空射撃も可能。
- ただし、砲、弾体両方があまりにも巨大な為、運用面に問題が多く、発射速度の遅さ、目標追従能力の悪さ等々、高速、高機動のギア戦には対応しきれていない。
- ネームシップのキファインゼル以下、ザンクティンゼル、ブリュッケ、4番艦の建造計画だったが、一番艦以降は全てキャンセルされている。
- グランガオン
- <搭乗者>セラフィータ
- 4体のギアの合体時に中枢となる機体。火属性のエーテルを増幅する機関を持つ。
- 本来翼は装備されていなかったが、マリンバッシャーと同様に汎用性を持たせるために取り付けた。
- 局地戦を得意とする機体。
- クレスケンス
- <搭乗者>エメラダ
- 本来、エアッドシステム搭載ギアの発展型として開発されたもの。
- エアッドの攻撃デバイス自体に、機体の機動制御をも行わせようという画期的なものでだったが、その制御系等のインターフェイス設計が難航し、その開発は半ば凍結された状態に置かれていた。
- しかし、エメラダを確保したカレルレンによって急遽開発が再開され、懸案となっていインターフェイス周りの問題は、エメラダが機体に物理融合することによって解決される。
- 両腕が無いのは、開発凍結時の名残りだが、頭部の翼状エアッドその代用を充分に果たしたため、あえて腕を廃し、替わりにサブスラスター装備による機動性の向上を図っている。
- 翼状エアッドは、それ自体がナノマシンで構成されており、誘導砲身、マニピュレーターとして機能する他、その自在な動きを利用したスタビライザー的役割も兼ねている。
- 名称はラテン語で「三日月」(正確には、「月」を表す「ルーナ」が必要)。
- 女性を表し、かつ、フェイにとって母性ではなく、逆に保護しなければならない不完全さを示す。
- 捲簾(ケンレン)
- 僧兵長時代のカレルレンの部下。イグニス防衛戦の際、ソフィアを護り戦死。
- 法院同様、そのパーソナルデータのみが保管され、ギアの中枢回路として再生処理を受けた。よって生前の人格は殆ど残っておらず、ほぼ全てが戦闘本能によって形成されている。
- ゴリアテ
- キスレブの誇る新造空中戦艦。開発時の仮艦名は「ギガント」。
- 処刑人(ミァン)によってもたらされたゲートキーパーを有する地上初の戦艦。
- しかし強奪後、バルトミサイルに被弾して墜落。あえなく海の藻屑と消えた。
- 名称は旧約聖書に登場するペリシテ人の戦士より。
- C1型ヴィエルジェ
- <搭乗者>ミァン
- 右肩に攻撃用エアッドを6基、左肩に防御用エアッドを1基装備した機体。
- 主装備がエアッドであり、特別なパイロットの専用機で常人には使いこなせない。
- 少数が生産された。
- G・エレメンツ
- <搭乗者>エレメンツ
- エレメンツが搭乗する4体のギアが合体することによりこの機体になる。
- 長く続いた戦争により兵士や国民に厭戦気分が広がることを懸念し、戦場のシンボルとなり兵士達の戦意を高揚させる目的で作られた。
- その効果は絶大で、Gエレメンツを称えた歌が作られ、ソラリスの音楽教科書にまで掲載された程である。――というのが公式データだが、事実はどうやら、設計者であるシタンの単なる趣味らしい。
- 全体の操縦はガッシュの搭乗者が行い、他の搭乗者は索敵やジェネレーターの出力管理などを行う。
- 合体後も各パーツのエーテル増幅機関は使用可能で各パイロットの属性能力を高めることが可能。
- シールドナイト
- <搭乗者>ブロイアー
- 要人や指揮官機の護衛を考えられて作られた機体。
- 両肩のシールド装備で防御力が高いうえ、シールドの上部にはロケットランチャーを装備し、先端には鋼の杭を射出し、敵機の装甲を打ち破るパイルバンカーが内蔵されている。
- 接近戦と遠距離戦両方に対応できる汎用性の高い機体。
- シューティア
- <搭乗者>リコ
- B管理委員会の技術実験と、リコの過激なセッティングが生み出したカスタム機。
- 機体各部は徹底したユニット化が図られており、損耗したパーツの即時換装が可能。
- 単位時間あたりの高出力化に重点を置いた結果、その稼働時間は極端に短くなってしまっている。もっとも、ほぼ全ての試合を数十秒という短時間で片付けてきたリコにとっては大きな問題ではなかった。
- ユグドラ乗船後は、機体の余剰スペースを利用したサブジェネレーター用の燃料タンクが追加装備されている。背部の大型ロケットは純正のスラスターではなく、開発途中で放棄された弾道弾ロケットの流用。
- リコのバトリングスタイルに合わせて、左腕にドリルクロー、脚部にグラインドローラーが装備されている。
- 名称はドイツ語で「牡牛座」。機体のイメージに合わせて付けられた。
- シャーカーン・ギア
- <搭乗者>シャーカーン
- 空中戦艦などに使用されている浮遊機関を小型化し搭載した試作ギア。
- 教会が管理するため、教会のシンボル兵器である刻印砲を搭載している。
- ゲートのエネルギーを抽出し、搭乗者のエーテル能力を高めることが可能。
- そのために背中のパイプが取り付けられている。
- スカイギーン
- <搭乗者>トロネ
- 高速強襲攻撃を得意とするギア。風属性のエーテルを増幅する機関を持つ。
- その性能は目覚しく、合体機能を省いた量産型の機体も作られた程。
- 合体時には翼となり、ジャンプ中や移動の際にバランスを取る役目を持つ。
- また、ブレードガッシュの背中に合体することが可能で、その形態は「スカイガッシュ」と呼ばれる。
- ゼノギアス
- <搭乗者>イド/フェイ
- ヴェルトール2がゾハルと接触したことにより、形態変化を起こした機体。
- その能力を極大にまで引き出され、その出力はORをも上回るほど。
- 従来の機構を使って燃料消費するものの、本来は燃料が無くても駆動可能。
- 超音速飛行時には、頭部と脚部が可変するようになっている。
- デウスを完全に破壊することが出来る唯一の機体。
- ゼノは「異質なもの」、ギアスは「歯車」を意味する。
- ゼプツェン
- <搭乗者>マリア
- M計画の中で生み出された、人機融合ギアの試作一号機。
- 操縦者の思考をダイレクトにギア中枢部に伝達し、機体操作はギア自身が行う。
- 「ギアに考えさせる」問題は、ヒトの脳とギア中枢部を直結させることで解決。
- 中枢回路には、M計画の副産物である人型特殊変異体ウェルスが転用され、これを解体・再構成するバイオサーキット技術の応用により、生体中枢制御回路の完成に至った。
- さらに、人工的な特異点を生み出すことで重力波を制御する技術を開発。試作機ゼプツェンに搭載した。
- ゼプツェンの中枢回路には、マリアの母クラウディアの脳が使われている。
- コクピットが無い為、マリアが頭の上に乗って操縦している。
- 名称は大鉄人17にそのモデルを求めたことから、ドイツ語で「17」。
- ソードナイト
- <搭乗者>ストラッキィ
- もともとは4本腕のギアとして開発されたが、操作系が複雑になりすぎて並のパイロットには扱えないという理由から、現在のようなチェーンソードに変わった。
- 汎用性こそ下がったが、格闘戦での攻撃力は大幅に向上している。
- 右腕の内装式ガトリングガンは、特殊部隊に配置後に取り付けられたもの。
- ソラリス空中戦艦
- 地上世界での単艦哨戒を任務として開発された。戦闘艦というよりは高速汎用空中母艦。
- 艦首部装備の重力制御機関の推進器兼空力スタビライザーで、三軸方向に自在に稼動。
- 本級では、スレイブジェネレーター、重力制御機関、粒子砲、リニアカタパルトなどを全てワンパッケージ化して量産効率を高めている。
- また機関系の艦首部装備に伴い、それら艤装は全て艦首部に集中配置されることになった。結果、艦中央部にこのサイズの艦としては極めて充実したギア運用スペースを設けることが可能。
- 天蓬(テンポウ)
- 僧兵長時代のカレルレンの部下。イグニス防衛戦の際、ソフィアを護り戦死。
- 法院同様、そのパーソナルデータのみが保管され、ギアの中枢回路として再生処理を受けた。よって生前の人格は殆ど残っておらず、ほぼ全てが戦闘本能によって形成されている。
- ドーラ
- <搭乗者>ヴァンダーカム
- かつて砂漠での主戦力が艦船であった時代に開発された対艦兵器。
- 艦船の強固な装甲板をも貫通できるように大口径のドーラ砲を装備し、艦砲にも耐えうる装甲が施されている。
- しかし、開発に長い年月を要し、主戦力は艦船からギアに移行。量産は見送られた。
- ハイシャオ
- <搭乗者>ドミニア、ケルビナ/ラムサス
- 海中での戦闘のみを考慮し設計された機体。
- 長い尻尾状の部分には、高精度のハイドロフォンを内蔵し、広範囲の索敵能力を持つソナーの役目を果たす。
- 両腕のクロー部分は電磁アームで、エアッドと同様のシステムを海中用に設計したもので遠隔操作が可能。搭乗者の能力が高ければ1人でも操作可能。
- 爆弾戦艦ヘヒト
- <搭乗者>ドミニア
- 船体内に大量の爆弾を搭載し、目的地に自艦ごと突入することを目的とした機体。
- 艦橋に備え付けられたギアは、目的地に着くまで本体に近づく敵を迎撃するためのもの。一機で船体全てをカバーすべく主装備をエアッドとした為、搭乗者には能力の高さが要求される。
- 目的地到着後はギア部を船体から切り離し、船体のみを投下させる。
- ハマー
- 人間をパーツとして機体内に組み込んだギア。
- 人格も残っており会話なども可能な、ギアというよりサイボーグに近い存在。
- 組み込んだ人間の何らかの欲望をエーテルとして変換できるため、欲望の強さがギアの強さにつながる。
- バルトミサイル
- ユグドラシル2世から装備された、大型戦術対艦ミサイル。
- 状況限定ながら対空・対潜能力も有し、反応弾頭の装備も可能。
- ミサイルの前身はアヴェ工廠、メルル・ジオット私設工房製「グングニルミサイル」だが、特にバルトらが改造を施したわけではなく、発見の際、威力を気に入ったバルトが勝手に命名した。
- その強大な破壊力故に、使用には発令所員の3分の2の合意が必須とされている。
- もっとも、バルトが独断で発射してしまっているあたり、有名無実のシステムではある。
- ちなみにこのバルトミサイル、発射プロセスにもバルトの趣味が如実に表されている。
- ブリッジ前面のコンソール(操作卓)の中心に、ガラスで保護された大きめのスイッチがあり、それを「拳で叩き割る」ことでミサイルを射出できるというシステムになっている。
- バントライン
- <搭乗者>ジェシー
- 近距離戦闘を得意とするギアを、遠距離から迎撃する為に作られた機体。
- 移動時には人型に変形可能な高い汎用性を併せ持つ。
- キャノンモード時の単体での砲撃は命中精度が低く、照準能力が高いギアとの連携が必要。
- さらに命中精度を上げるため、コクピットブロックを弾丸とし、搭乗者が弾道の操作をできるよう設計された。
- ブリガンディア
- <搭乗者>バルト
- アヴェで発掘されたギアを基に、バルトの為にカスタマイズされたユグドラ整備斑の血と汗と涙の結晶。
- エクステリアデザインは、バルトの要望でファティマ王朝に伝わるギアに似せたものに。
- 近距離用装備が施されていたが、主武装のロッド装備と、それに伴う腕部と脚部の強化、ロッド攻撃にエネルギーダメージを付加させる目的で肩部に内蔵された、メインジェネレーター直結コンデンサーなど、大幅に改造が施されている。
- 主戦場が砂漠であるため、脚部にホバースラスターが装備されており、機体が砂に沈み込むのを防ぐ他、ホバリングによる高速移動が可能となっている。
- また、関節各所に熱砂シーリングが施され、砂による稼動部分の損傷を防いでいる。
- 14歳の時に初陣を飾り、初のギア戦にも全く臆せず、ミロクも驚き呆れるほどのはしゃぎ振りだった。
- 頭部の羽飾りとアイパッチは海賊らしい外観に拘って付けられた。
- 名称はケルト神話の地母神「ブリカンティア」と、海賊を表す言葉「ブリギャンド」からの造語。
- フリゲート艦
- ソラリス空中艦群の中でも最新最精鋭であり、政府要人座乗艦のエスコートが主任務。
- そのため武装は過剰なまでに強力で、しかもその全てが粒子砲などの非実体弾火器。
- また、その性格上ギアの搭載能力は無く、自動化の結果、運用人数も12名と少数で、艦というよりは超大型航空機的な性格を際立たせている。
- その要人の護衛という任務上、ソラリス市民はおろか、軍人にも馴染みの薄い艦。
- ブレードガッシュ
- <搭乗者>ドミニア
- もともとの機体名は「ガッシュ」であり、様々な武器を装備可能。
- だが搭乗者であるドミニアが剣の扱いを得意としており、エーテル剣を装備することが多かった為、この名前で呼ばれることになる。
- Gエレメンツに合体時には「目」の役目をする機体で、索敵能力は高い。
- また、他の3機とそれぞれ合体し、状況に応じた属性をエーテル剣に持たせて攻撃可能。
- ヘイムダル
- <搭乗者>シタン
- 500年前の大戦中に設計・製造された汎用戦闘ギアのカスタム機。
- 同時に発掘されたブリガンディアとは、基本パーツの約八割を共有。
- 元来は同型機だったが、外装とアビオニクスは全くの別物が実装されており、特にアビオニクスに至っては、ブリガンディアとは対照的に、光学機器、センサー類の増設強化が図られていた。
- この事から、遠距離戦、索敵任務を主として兵装が施された機体だったと推察される。
- ユグドラスタッフにより、過剰な出力設定と過敏すぎる駆動系のセッティングが施され、常人では扱えないほどのラジカルな機体として生まれ変わる。
- 遠距離索敵能力と近接戦闘力双方の獲得を意味するが、それを活かす者がいなかった。
- セッティングによって用兵上の殆どの状況に対処できる汎用性の高い機体。
- 名称は北欧神話に登場する、何者をも見逃さない目を持つ神「ヘイムダル」より。
- シタンは剣士なので、元々はジークフリードの得物の名「グングニル」が用意されていたが、シタンの学者としての面等からヘイムダルに変更された。
- 碧玉要塞
- 500年前、ロニによって発見された移動要塞。
- ニサン地下に霊廟として、ギア・バーラーと共に封印されている。
- 網膜パターンによるロックシステム、高火力の長距離砲を有する。
- OPムービーでシャトルを撃ち落としていたのと同一の物。
- マリンバッシャー
- <搭乗者>ケルビナ
- エレメンツの機体はそれぞれ得意な戦域があり、その名の通り海戦を得意とする機体。
- 本来は完全な海域用だったが、地上戦や空中戦にも対応させるべく改装が施された。
- 水属性のエーテルを増幅する機関を持つ。
- メルカバー
- デウスシステムの、言葉通り外殻となる直径80kmの巨大戦略制圧母艦。
- 表面に刻まれたスリット部分にデウスの機動端末アイオーンを擁する。
- 名称は「天の車」という意味の言葉から。
- ユグドラシル
- 艦の前身は、アヴェ旧ファティマ朝末期のラグンバルド1世の治世に計画された、第3次エオホズ法に基づく建艦計画の第1番艦。仮称艦名は「C(カイザー)」。
- アルファベット語圏ではそれそのものを伝える際、頭文字にした単語で伝えることがある。これがドイツ語圏なら「A=アントン」「B=ベルタ」となり、「C=カイザー」「D=ドーラ」と続く。
- このことから現在の艦型となる以前、2つの試作艦があったことがうかがえる。
- 正式艦名には「シグリット」が予定されていたが、ラグンバルドの嫡子、エドバルト4世の対キスレブ和平交渉が歩み寄りを見せたため、相互軍縮の対象となっていた。
- その際、同型の2番艦ともども廃艦となり、モスポール状態で封印されている。
- それから数年後、シャーカーンによるクーデターの混乱中、2艦ともに行方不明に。
- このうち1番艦にあったものは、実はバルト救出の際にシグルドらの手により奪取されており、アヴェ近郊の砂漠で反政府ゲリラの主力艦「ユグドラシル」として第二の人生を歩んでいる。
- 後にイドの手により破壊されるが、数奇な運命に導かれ、同型の艦の入手に成功。
- 言うまでもなく、行方不明となっていたシグリット級の2番艦。
- 同型・同装備であったその2番艦は「ユグドラシル2世」と命名された。
- ――内部構造
- 大きな特徴として、徹底したモジュール構造(各構成部分が独立した構造)の採用。
- 艦全体は5モジュールで構成されており、発令所(ブリッジ)、機関部(艦中央)、武装部(艦首上部)、格納部(艦首下部)、砂漠用の流動化装置と砂用ポンプ、推進外輪などを納めた機械推進部(艦尾部)となっている。
- 各モジュールは完全独立稼動が可能で、特に発令部と武装部は単体で分離できる。
- こういったモジュール構造の利点は、装備の変更や更新が比較的容易であることと、装備運用とダメージ・コントロール(機体損傷時の応急処置)がスムーズに行えることなど。
- ――ブリッジ(発令所)
- 艦内の各部を全てリモートコントロールできる、艦艇運用の要となる場所。
- 中央に見えるのは潜望鏡で、潜水艦同様、砂中から表層の状況を肉眼で確認できる。
- コンソール周辺のごく近代的な構造と比較してそのクラシックさに驚くが、多分にバルトの趣味。
- ――機関室
- スレイブジェネレーターを中核とする、艦の動力を統制するモジュール。
- 「おやっさん」こと機関長が常駐し、各種回路の点検に勤しんでいる。
- SGのタイプは、アヴェ界隈で発掘された中でも最大規模のファティマ廠第25期発掘型。
- ――艦首カタパルト上部
- 25口径の1.2スール砲を納めた、隠見式連装砲塔2基を中核とする武装部。
- ギア発着時は上部に展開し、カタパルトが露出する構造。
- なお、主砲の後部には追加装備用の予備タレット(砲座)が用意されている。
- これは初代ではソナーポッドと予備弾薬の格納庫として利用されていたが、ユグドラシル2世ではバルトミサイルのランチャーとして改造された。
- ――艦首カタパルト下部
- 45カーンの射出能力を誇るリニアカタパルトを備え、最大20機のギア運用が可能な格納部。
- また、潜砂艦独特の装備として、砕氷船などに見られるトリミングタンクがある。
- これは艦内に砂を取り入れ、急速に移動させることで艦首の角度を大幅に変えるもので、自重で潜砂速度を上げる効果を持つ。
- これに粉粒化動翼(砂を振動させ、流体のような性能を持たせることで砂中の潜航を可能とする装置)と推進外輪を加え、潜砂艦の機動力を構成している。
- ユグドラシル3世
- 2世をベースに、シェバトで大幅な改良を施した艦。
- 艦尾に巨大なブースターを連結し、巨大な推進翼を備え、高速航行をも可能な万能艦。
- ブースターの機能は飛行能力の付加以外に、艦自体を巨大なキャノン砲として使用可能。
- その場合、ブースターは変形し、ライフルのグリップとストックのような形状を呈する。
- なお、ブースター下部から延びている巨大なケーブルは、外部のスレイブジェネレーターから一時的に出力を得る際に使用されるもので、ユグドラシルIVに連結することを想定した装備。
- 連結状態下では、単体では不可能だったエネルギー量の制御とごく短時間でのエネルギーチャージが可能。それに伴い、ゼプツェン級のグラビトン砲を発射することが出来る。
- ユグドラシルIV
- 恒星間航行船エルドリッジに搭載されていた大型の強襲揚陸艦。
- 一連のユグドラシルシリーズとは基本的に無関係。
- エルドリッジが墜落した際、地表付近でその係留ブロックから切り離され、ノアトゥン近辺に埋没。その後、ロニの手によって発掘・改修され、来るべき大戦の切り札としてノアトゥン内に封印されていた。
- やがてその存在は、ゼファーを始めとするごく一部の人間のみの知るところとなった。
- なお、ユグドラシルが3世に改修された際、このIVと合体できる仕様が加えられている。
- この際の各指令系統は全て3に依存し、それによって少人数での運用が可能。
- 緊急時は切り離しも容易であり、効果的な改良であるといえる。
- ――変形後
- 本来の用途が揚陸艦であったIVは、上陸後の作戦行動をよりスムーズに行うため、設計当初からギア形態への変形が決定されていた。
- 揚陸艦から変形するギアがこの規模。
- エルドリッジが出港した本星のギアのサイズは推して知るべし。
- 元が艦艇であるだけに、全身のあらゆる場所に小規模の火器が搭載されているのも大きな特徴。
- ライトフォージ級
- ラムサスとミァンが搭乗し、熱砂でユグドラシルと対峙したソラリスの新鋭潜砂艦。
- ユグドラのような推進外輪は無く、艦尾両脇の推進翼表面に最新型の超流動推進器を備えている。
- これにより、耐圧船殻を貫通していた長大な外輪用ドライブシャフトが不要となり、船体の強度も従来艦より大幅に増している。
- また、その推進器を稼動させるスレイブジェネレーターは、発掘品ではなく、ソラリスが独自に開発したもので、本級に試験的に採用された。
- 結果、本級は潜砂艦としては異例の速度性能と静寂姓を持つに至っている。
- レンマーツォ
- <搭乗者>ビリー
- 一般的なエトーン・ギアのカスタム機として、「教会」本部で試作された機体。
- フレーム構造にソラリスギア製造技術の名残りが見られる。
- 外観はエトーン・ギアと同様だが、二次装甲の強化や固定武器の拡充など戦闘力を向上。
- 武装の特徴は、その全てが固定、もしくは機体内に格納される方式である点。
- 特に両腕の回転弾倉式のアームガンは強力で、通常軍用ギアのマシンガンを遥かに上回る。
- また、高性能ターゲットディスプレイを装備しており、命中率も非常に高くなっている。
- 頭部の長い帯状突起物は識別ポールと対死霊レーダーを兼ねたもの。
- 背部のマントはエトーンの正装。
- 名称は中国(北京)語で「射手座」。漢字では「人馬座」でケンタウロスのこと。
- ワイバーン
- <搭乗者>ラムサス
- ラムサスが天帝カインに恩賜された専用ギア。
- ゲブラー総司令官に相応しい「究極のギア」という開発コンセプトの下、シタンが基本設計にあたり、ゲブラー兵器開発部門が総力を結集して開発した機体。
- その為、全てが専用部品で構成されたワンオフタイプのギア。
- 高出力の大型ジェネレーターを三基搭載し、両肩アクティブアーマー内のプラズマ推進機、ロングスタビライザーの採用により、重量級ギアに匹敵する装甲を持ちながら、軽量級並の運動性が確保されている。
- 肩部アクティブアーマー下に接続されているパーツは、誘導砲身型の大型エアッド。
- サブジェネレーター内蔵のそれは、蓄電型エアッドに比して数倍する出力を誇る。
- また、格闘戦用クローとしても機能。誘導砲身間のビーム刃によって対象を切断可能。
- 主武装の剣は、浅い反りの片刃の鍛造刀で、過去に粛清された地上民族から接収した。
- 最新技術が投入されているが、ナノ技術や人機融合などの次世代技術は採用されていない。
- ワンドナイト
- <搭乗者>ランク/ヘルムホルツ
- 機動力が高く、本来は強行偵察用に作られた機体。
- 小型ホバーを搭載し、両肩の羽でバランスを取ることで、短時間の飛行が可能。
- 当初は各機体のテストも兼ねて、ゲブラー隊の5人に合わせて5種類のギアが用意され、ランクはランスナイトというギアに乗る予定だった。
- しかし、輸送中の襲撃で失われ、急遽ワンドナイトがもう1機後送された。
- パワービームは射程距離も長く、強襲時には敵の先手をとり、撹乱することが可能。
■ TOP ■
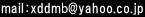
Copyright © 2008 SQUARE ENIX CO., LTD All Rights Reserved